就職氷河期――1993年から2004年ごろに社会に出た世代。
「希望しても正社員になれない」「ブラック企業でも辞められない」「頑張っても報われない」
そんな“理不尽を飲み込むしかなかった時代”を生き抜いてきた人たちがいます。
近年ようやく、政府や企業による「氷河期世代支援」が進みつつありますが、本当にそれで十分なのでしょうか?
この記事では、支援の本質は“再雇用”や“職業訓練”ではなく、“ハラスメントや長年の搾取への償い”であるべきではないかという視点から掘り下げます。
就職難だけが問題だったわけじゃない
氷河期世代が直面したのは、「仕事がない」という問題だけではありません。
彼らが社会に出た90年代後半から2000年代初頭は、労働環境がもっとも劣悪だった時期でもありました。
パワハラ・モラハラが“教育”と呼ばれていた時代
-
上司に怒鳴られる
-
無理なノルマを課される
-
深夜までの残業が当たり前
-
怪我をしても「気合で乗り切れ」と言われる
これらはすべて、**「根性」「やる気」「社会人として当然」**という言葉で正当化されていました。
今であれば即・問題行為とされるようなパワハラが、氷河期世代には“日常”だったのです。
サービス残業が常態化していた現実
長時間労働と未払い残業(サービス残業)は、当時の企業文化そのものでした。
「終電まで働くのは当たり前」
「残業代の話をするやつは空気が読めない」
そんな空気の中で、体と心をすり減らしながら働き続けた人が大勢います。
なぜ“支援”だけでは報われないのか?
近年の氷河期世代支援策には、雇用機会の創出、スキルアップ研修、就職フェアなどがあります。
それ自体は歓迎すべきことですが、どこかで**「これで十分でしょ?」という空気**を感じることはないでしょうか。
支援の前に“謝罪”が必要では?
本来、氷河期世代への支援は「救済」ではなく、「償い」であるべきです。
-
体を壊しても「甘え」と言われたこと
-
キャリアの分断が起きても「自己責任」で済まされたこと
-
社会全体が黙認してきた“働かせ放題”の構造
こうした歴史を踏まえれば、今すべきは**「もう一度チャンスをあげる」ことではなく、「あのとき奪ったものへの謝罪と回復」**ではないでしょうか。
支援策を“本質的な補償”に変えるために
では、どのような支援が“本当の意味での償い”となりうるのでしょうか?
ここでは具体的な提案と、当事者視点の重要性を見ていきます。
長期的・継続的な支援こそが必要
短期間の研修や一時的な雇用では、長年積み重ねられたキャリアの断絶や自尊心の傷は癒せません。
必要なのは、「一時的な支援」で終わらせずに、安心して人生を再設計できる環境を整えることです。
たとえば:
-
年齢を問わない正社員登用の機会拡大
-
経済的基盤を支える手当や奨励金の支給
-
心理的サポートや再教育プログラムの長期提供
当事者の声を政策に反映させる
支援策の多くが「上から目線」になってしまう原因は、当事者の声が政策に反映されていないからです。
本当はこうしてほしい、こんなことで悩んできた――
そうした「現場のリアル」を拾い上げ、支援内容に落とし込むことで、初めて“誠実な支援”が実現します。
氷河期世代を“被害者”として語ることの意味
「被害者ぶるな」という言葉があります。
けれど、氷河期世代は「ぶっている」のではなく、実際に制度的な被害を受けた世代です。
歴史に残る“労働搾取の時代”を語り継ぐべき
日本社会にとって、氷河期世代は**“失われた労働倫理”の象徴**とも言えます。
同じ過ちを繰り返さないためには、過去を直視し、明確に記録し、語り続けなければなりません。
「支援」ではなく「尊厳の回復」を
氷河期世代が求めているのは、恵みや施しではなく、尊厳の回復です。
「あなたたちは間違っていなかった」「あの苦しみは無駄じゃなかった」
そう社会が言葉と行動で示すことが、最大の支援になるのです。
まとめ|支援は“謝罪の第一歩”から始まる
-
氷河期世代は、就職難だけでなく、パワハラ・長時間労働の被害者でもある
-
支援策は「再就職のチャンス」だけでなく、「過去の搾取への償い」であるべき
-
当事者の声を反映し、尊厳を回復できる支援の形が求められている
-
これは労働の未来をよりよくするための“社会全体の責任”
今、必要なのは「救ってあげよう」ではなく、「ともに誤りを正そう」という姿勢です。
氷河期世代の苦しみを、“歴史のひとコマ”で終わらせないために、私たちは何ができるか――その問いから目をそらしてはいけません。

















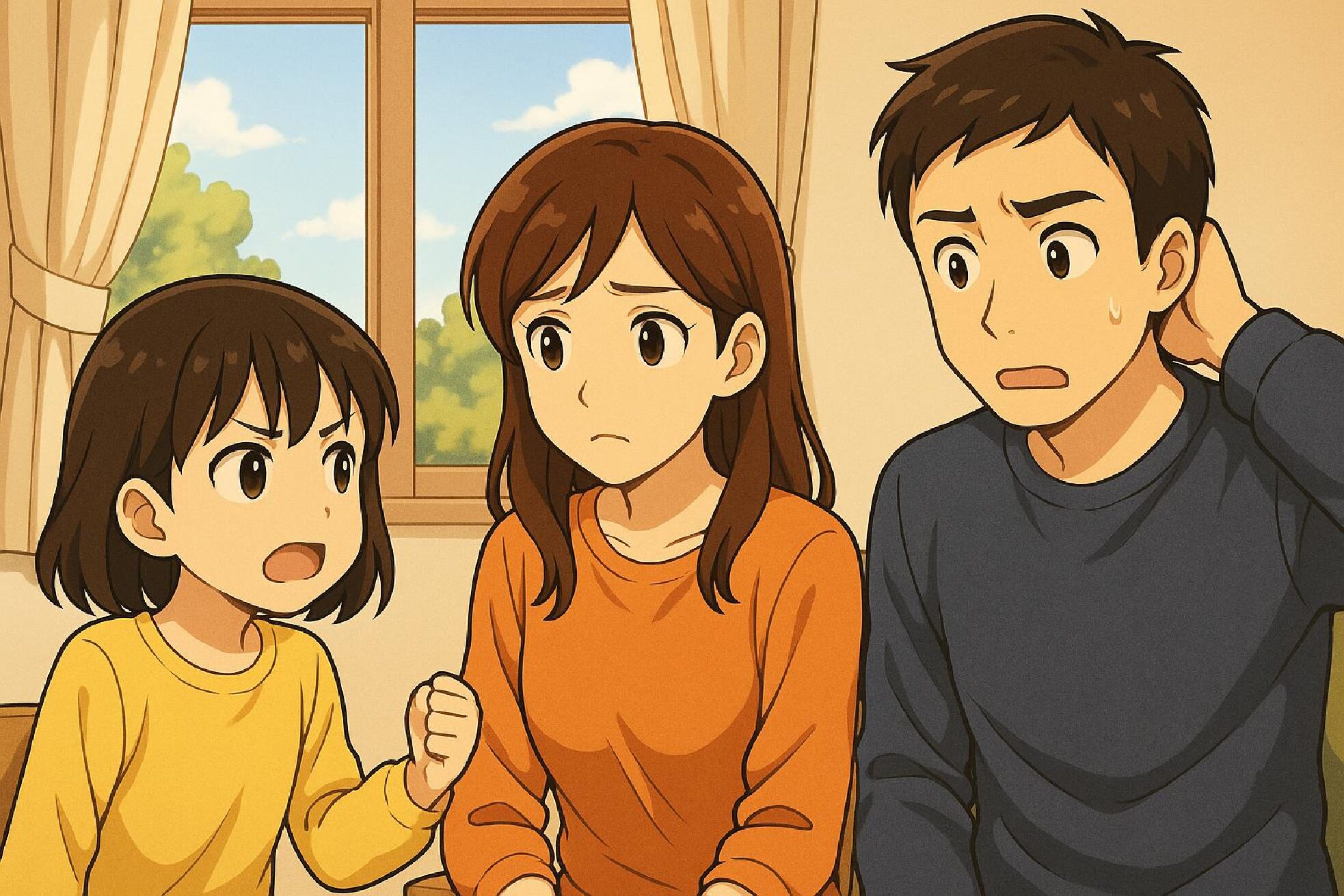
コメント