~農業政策はどう変わる?子どもと一緒に考える日本の食の未来~
「お米が高くなった?」「野菜が少ない?」
最近、スーパーで“食べものの変化”を感じていませんか?
実は今、「食料農業農村基本法 改正」という大きな動きが進んでいます。
聞き慣れない言葉ですが、これは日本の食や農業を支える“ルールの柱”になる法律です。
この記事では、
✅ この法律はどんな内容なのか?
✅ なぜ改正されるのか?
✅ 私たちの暮らしにどう関係してくるのか?
を、親子で読めるくらいやさしく&わかりやすく解説します🧑🌾👧🍙
1. 「食料農業農村基本法」ってなに?
まず、「食料農業農村基本法」というのは、
1999年に制定された、日本の“食と農の未来”を考えるための大きな枠組みです。
この法律では、
-
日本の農業をどう守るか
-
食料自給率をどう高めるか
-
農村地域をどう元気にするか
などが決められていて、国の農業政策の基本方針になっています。
つまり、「ごはんを安心して食べ続けられるようにするにはどうすればいいか?」を
ずっと考え続けてきた大事なルールなんですね🍚✨
2. なぜ今、法律を“改正”するの?
では、なぜ今「食料農業農村基本法 改正」が進められているのでしょうか?
理由は主に3つあります👇
🌡️① 異常気象・災害で農作物の安定供給が難しくなってきた
台風や猛暑、集中豪雨などが続き、作物の収穫が不安定に。
👨🌾② 農業人口の高齢化と担い手不足
農家の平均年齢は現在約68歳。後継者不足が深刻です。
🌏③ 世界的な食料危機の影響
輸入に頼ると、戦争や国際的トラブルで物価高騰・品薄になるリスクも。
これらの課題に対応するため、
「今のルールでは間に合わない。もっと実効性ある新しい方針をつくろう」という流れが生まれているのです。
3. 改正後、農業政策はどう変わるの?
2024年末~2025年にかけての「食料農業農村基本法 改正案」では、次のようなポイントが注目されています👇
✅ 食料安全保障の強化
→ 自分の国でちゃんと食料を作れるようにしよう!という考えが強調されます。
✅ 若い世代・企業の参入を後押し
→ 農業を“働きたい業種”にするための支援策が検討中。ITやスマート農業も注目。
✅ 環境にやさしい農業への転換
→ 持続可能な農業を進め、気候変動に対応できる農業へ。
✅ 農村の役割の再評価
→ 農村は「食料をつくる場所」だけでなく、「自然・文化・人のつながり」を守る大切な地域として見直されます。
4. 子どもと一緒に考えよう「未来のごはん」
この法改正は、大人だけの話ではありません。
「未来のごはんを誰がどう作るのか?」は、子どもたち自身にも関係あることです。
例えば…
-
近くの直売所で野菜を買ってみる
-
家庭菜園を親子で始めてみる
-
農業体験に行って「作る人の想い」に触れてみる
こんな小さな体験から、「食」と「農」の大切さを自然に学べます🌱
5. 私たちにできることは?
「法律改正」と聞くと難しく感じますが、実は家庭でできることもたくさんあります。
✅ 地元の食材を選ぶ(地産地消)
✅ 子どもと一緒に食べものの話をする
✅ 農家さんの声に耳を傾けてみる
✅ フードロス(食品ロス)を減らす工夫をする
これらはすべて、農業を支える行動のひとつです🍅✨
✅ まとめ|「未来のごはん」は、今から一緒に守っていくもの
-
「食料農業農村基本法 改正」は、日本の食と農の未来を大きく左右する重要な動き
-
食料自給率や農業の担い手不足など、身近で切実な課題が背景にある
-
改正により、持続可能で安心できる“ごはんの未来”を目指していく
私たち消費者も、「何を選ぶか」「どう食べるか」で、未来を支える一員になれます。
子どもと一緒に、「食べるって、どういうこと?」を考える春にしてみませんか?🌾👩👧🍙
📌 参考リンク(農林水産省)
食料・農業・農村基本法について|農林水産省
















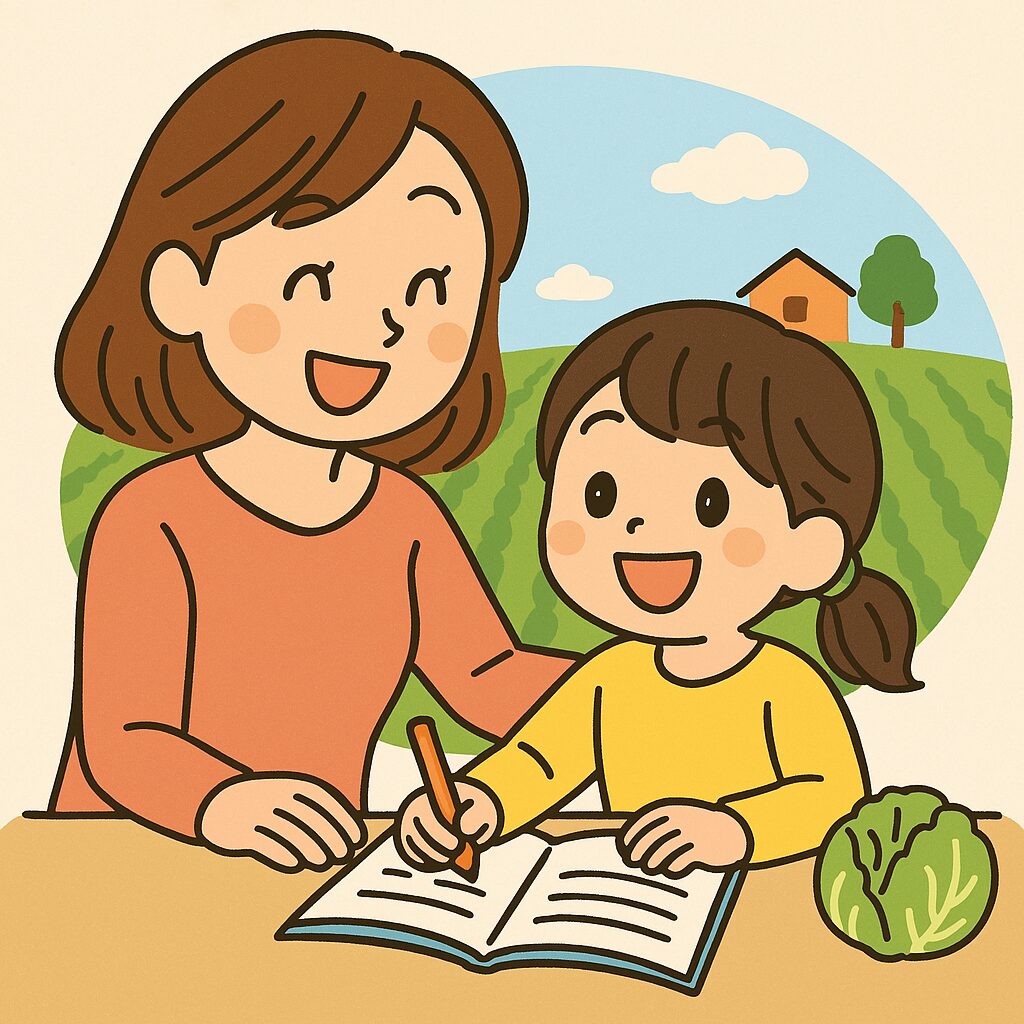

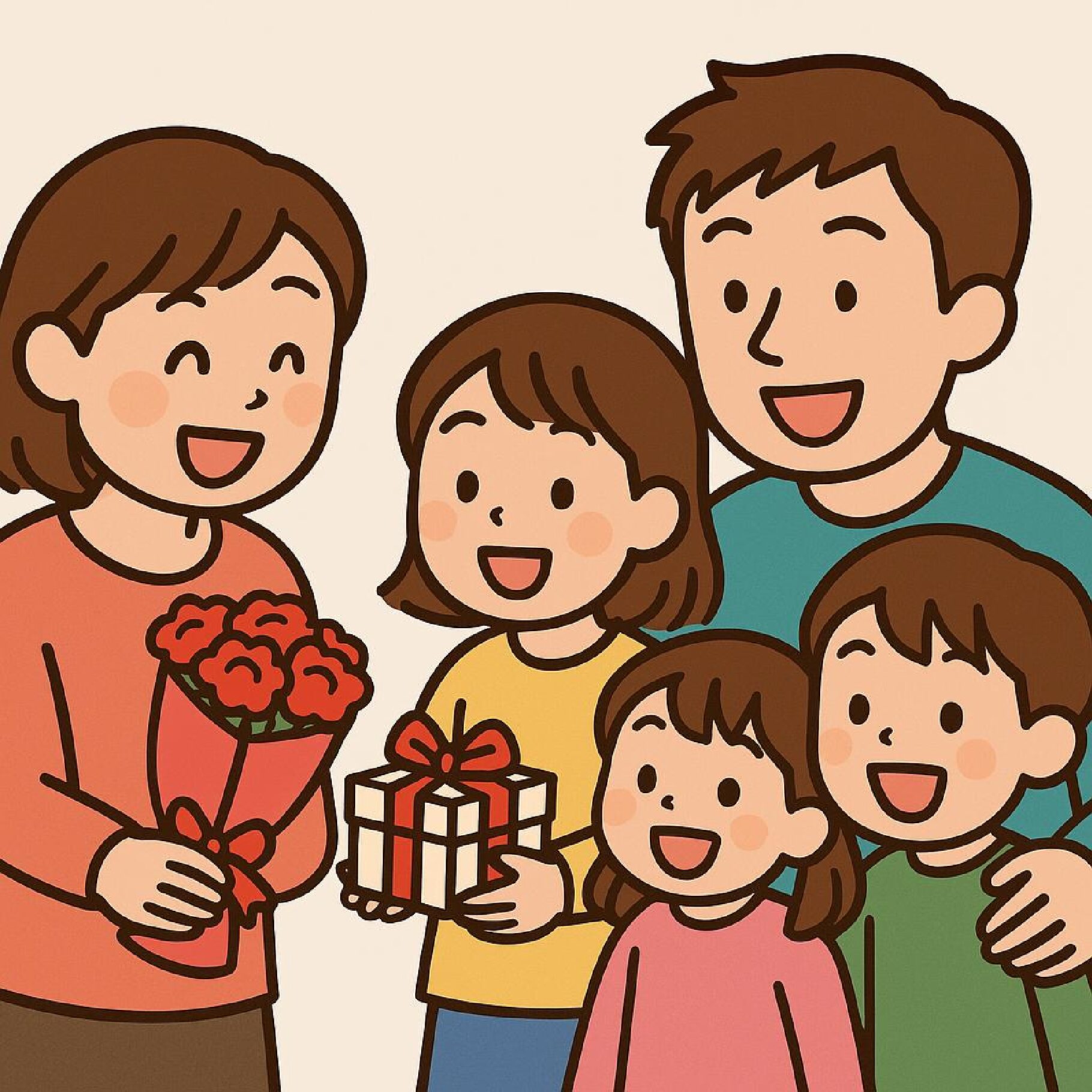
コメント