「怒鳴られるのが当たり前だった」「ミスをしたら机を叩かれた」「体調を崩しても“甘え”と一蹴された」
こうした話を聞いて「昔はそんな時代だったから」と片付けていませんか?
今なら“完全にパワハラ”と認定される行為も、**氷河期世代(1970年代後半〜1980年代生まれ)**が若手社員だった頃には「普通のこと」として職場にあふれていました。
この記事では、なぜそのようなパワハラが許容され、問題視されなかったのかを、時代背景・企業文化・社会構造の3つの視点から読み解いていきます。
氷河期世代が働き始めた時代とは?
まず、氷河期世代が社会に出た「就職氷河期」とはどんな時代だったのでしょうか。
バブル崩壊後の“買い手市場”
1990年代初頭にバブルが崩壊し、日本経済は深刻な不況に突入しました。それに伴い、企業は採用を大幅に縮小。大学を卒業しても正社員として就職できない人が続出しました。
特に1993年〜2004年ごろに卒業した世代は「就職氷河期」と呼ばれ、社会に出た直後から厳しい競争と過剰な自己責任を背負わされてきたのです。
「働けるだけマシ」という諦めの感覚
当時の若者は、「正社員になれたらラッキー」「文句を言わずに働くべき」という空気の中で社会人としてのスタートを切っています。
職場で理不尽な扱いを受けても、「辞めたら次がない」「怒られるのは当然」と自分を納得させてしまう風潮が強くありました。
パワハラが「当たり前」だった企業文化
ではなぜ、そんな時代に職場のパワハラが当然のように受け入れられていたのでしょうか?
昭和型マネジメントの名残
氷河期世代が入社した1990年代〜2000年代前半の企業には、依然として昭和の高度経済成長期の価値観が根強く残っていました。
-
上司は厳しくてナンボ
-
「見て盗め」式の教育
-
忍耐力=仕事力とみなされる風潮
こうした価値観のもと、「怒鳴る」「詰める」「人格を否定する」ような行為が**“教育”として正当化されていた**のです。
成果主義と圧力の同居
バブル崩壊後、企業は成果主義を導入し始めました。すると、成果を出せない者は徹底的に責められるようになり、職場の空気はピリピリ。
成果を出す者も、そのプレッシャーと孤独感にさらされ、余裕を失い、下の世代に対して過剰な厳しさを向けるという悪循環が生まれました。
なぜ当時はパワハラが問題にならなかったのか?
今でこそ、パワハラは「企業のリスク」「法的にアウト」と明確に語られる時代ですが、当時はなぜそうではなかったのでしょうか?
社会全体が「声を上げる=甘え」としていた
2000年代前半までは、「耐えることが美徳」「文句を言うやつは甘えている」という空気が支配的でした。
職場でパワハラを受けても、「そんなのどこに行ってもあるよ」「我慢できないのは自分の弱さ」と返されるだけ。被害者の声が無視される構造が社会全体に広がっていたのです。
法整備が遅れていた
厚生労働省が「職場のパワーハラスメント対策マニュアル」を公表したのは2012年。
パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が企業に義務付けられたのはようやく2020年からです。
つまり、氷河期世代が20〜30代の頃には**「パワハラ」という言葉すら存在していなかった**のです。
氷河期世代が今も抱える“見えない傷”
長年、理不尽な職場環境に耐えてきた氷河期世代。今、その影響はどこに現れているのでしょうか?
自信を持てない、部下に厳しくなる…
-
「怒られない=認められていない」と思ってしまう
-
部下にも“厳しさ”を求めてしまう
-
褒められ慣れておらず、自分を過小評価する傾向
こうした傾向は、若い世代とのギャップや、組織内での孤立感にもつながっています。
「声を上げない文化」が次世代に影響している
自分が我慢してきた分、「若者ももっと耐えるべき」と考えてしまうケースもあります。
これは無意識のうちに、パワハラの再生産を生む原因にもなっています。
これからの企業が果たすべき役割
氷河期世代の過去の経験を風化させず、今後の職場環境に活かすために、企業や社会は何をすべきでしょうか。
「昔の常識は非常識」だと認識すること
時代は変わりました。「当たり前だったから仕方ない」では済まされないのです。
企業は、過去の慣習を正当化しないという姿勢を明確に打ち出す必要があります。
氷河期世代へのリカバリーも必要
今なお、正社員になれなかった、キャリア形成に支障があったなど、氷河期世代は社会的に取り残された経験を持っています。
企業がこの世代に対して、学び直しやキャリア支援の機会を提供することは、未来への投資でもあります。
まとめ|過去を見つめ、未来を変える一歩に
-
氷河期世代は、就職難と過酷な職場文化の中で、パワハラを“当たり前”として受け入れざるを得なかった
-
パワハラが許されていたのは、時代背景と社会構造の問題
-
今こそ、過去を振り返り、「沈黙してきた世代」の声をすくい上げることが求められている
かつての「当たり前」によって傷ついた人々の経験をなかったことにはできません。でも、それを見つめ直すことで、今と未来の働き方を変えることはできるはずです。
もしあなたも、あの時代を生きてきた一人なら――
「もう我慢しなくていい」
そう伝えられる社会を、いっしょにつくっていきませんか?
● 厚生労働省|職場のハラスメント対策ページ
パワハラの定義や法的背景を補足
👉 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126546.html

















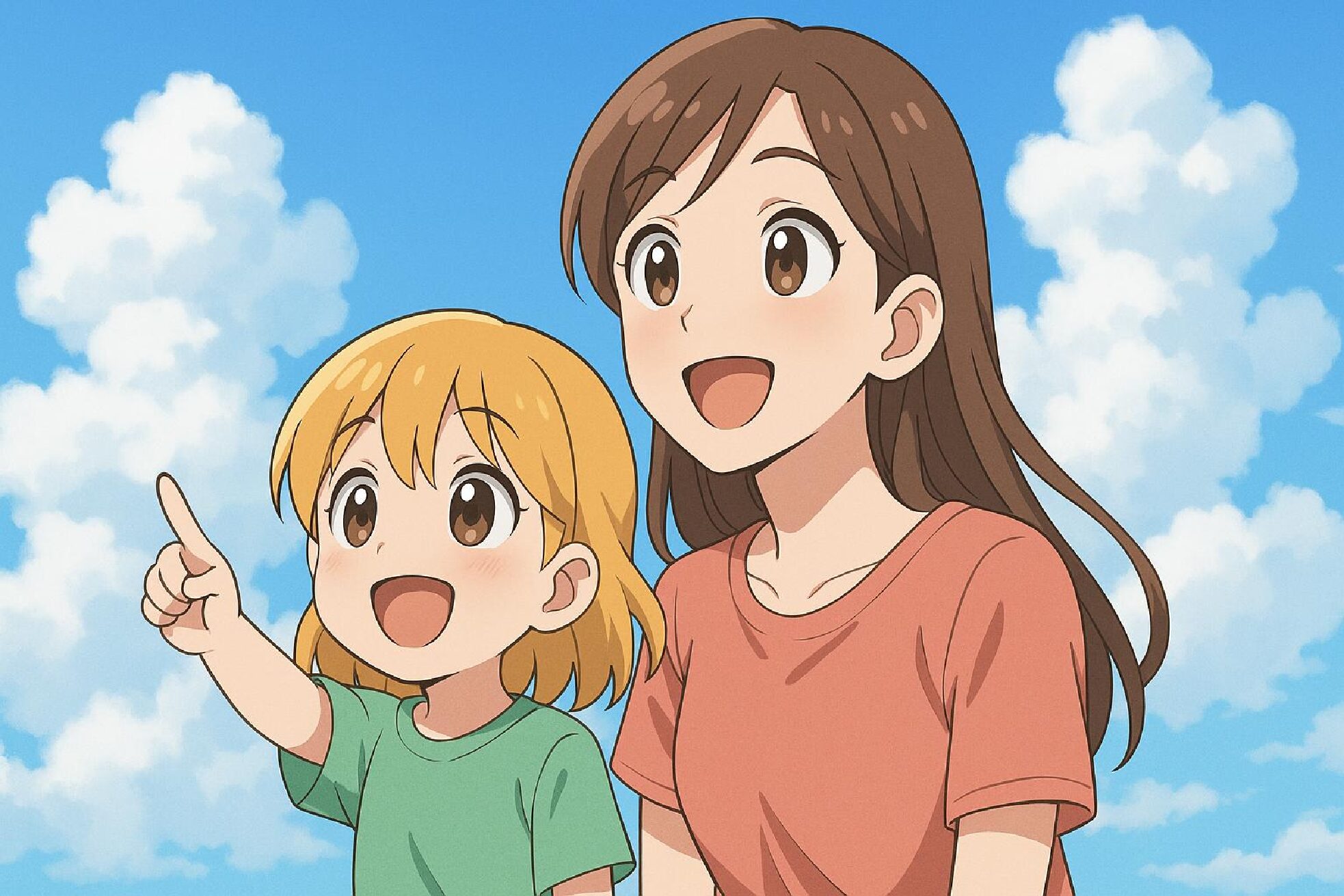

コメント